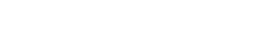パニック障害とは
①ある日突然、理由もなく動悸(心臓のドキドキ)やめまい、呼吸困難の症状が起こります。
②激しい不安・恐怖が発作的に起こり、気が狂って死んでしまうのではないかと感じます。
③このようにさまざまな身体症状を伴ったパニック発作を繰り返すのが特徴です。
④通常、発作は10分程度でピークに達し、数十分から1時間くらいで自然に治まります。
⑤自分では心臓発作だと感じて、救急車で病院に運ばれても、心電図等で特に異常が無く、医師から「どこも悪くないですよ」などと言われ、そのまま帰されてしまうケースがしばしばあります。
パニック障害の一般的な症状
①心悸亢進といって心臓がドキドキする、体の全体がドキンドキンという、心臓をギュッと掴まれたような感じ、喉から心臓が飛び出しそうな感じ。
②呼吸困難では、息苦しい、呼吸が早くなる、空気が薄く感じる、息の吸い方吐き方がわからない、狭いところに閉じ込められた感じ、喉がえずくなど。
③めまいでは、ふらつく感じ、頭が軽くなる、頭の血管がプツンとした感じ、頭を後ろに引っ張られるような感じ、頭から血が抜けていくような感じ。
④腹部の不快感では、お腹がグニャグニャして変な感じ、胃がギュッと引っ張り上げられる感じ。
⑤非現実感(離人感)では、自分が自分でない感じ、自分をもう一人の自分が見ている感じ、頭に霞がかかっている感じ、ベールをかぶっている感じ、雲の上を歩いている感じ。
⑥その他、汗をかく、身体や手足の震え、吐き気、胸の痛み、常軌を逸する感覚、気が狂う感じ、死ぬのではないかという恐れ、しびれ感、うずき感、寒気、ほてりなど。
⑦ここに挙げた症状で一貫していることは、常に激しい「不安感」や「恐怖感」があることです。その不安というのは「いても立ってもいられない」「大声で叫びたくなる」「走り出したくなる」「どうしようも出来ない」といったような不安で、心の底からわき起こってくる感じです。
パニック発作の症状の起こり方には以下の三つのケースがあります。
◎1つは、突然に起こるケース。場所や状況に関係なく、不意に起こる発作。
◎2つ目は、ある場所 や状況に限って起こるケース。恐怖感や緊張感を感じるような場所や状況におかれたときに起こる発作。
◎3つ目は上記の二つの混在型で、ある状況のもとで、発作は必ず起こるわけではなく、他の症状と合併して起こる発作。
パニック発作の起こりやすい場所や状況とは、次のような場合です。乗り物の中(電車・バス・飛行機・渋滞中の車など)、狭い空間(エレベーター・トンネル の中など)、人込みの中(デパート・スーパー・雑踏の中)、公の場(病院や銀行の待ち時間、歯科医院、美容室や式典の会場など)、一人の時(風呂に入って いる時や夜間の散歩、知らない町中など、誰にも助けを求められない状況のとき)は、緊張をしたり不安を感じやすいために、発作が起こりやすくなります。ま た、夜間や就寝中にも突然発作が起きて、目を覚ますこともあります。
強迫性障害とは
①強迫観念;自分の意に反して、つまらない考えが繰り返し浮かんできて、抑えようとしても抑えられない
②強迫行為;そのような無意味な考えを打ち消そうとして、無意味な行為を繰り返す
③強迫性障害は、このような強迫観念や強迫行為を主症状とする神経症です。
④例として、何度も繰り返して手を洗う、戸締まりを確認するなどがよく見られます。
強迫性障害の発病確率
人が一生のうち一度はかかる確率は2.5%で、女性のほうが男性よりも若干多く、初診時の平均年齢は約30歳です。 30%の頻度でうつ病を合併しており、その他恐怖症・社交不安障害・全般性不安障害・パニック障害などの不安障害を10%程度の頻度で合併しています
強迫性障害の原因は何か
特別なきっかけなしに徐々に発症してくる場合が多く、原因もいわゆる心因(心理的・環境的原因)よりも、大脳基底核、辺縁系(帯状回)、前頭前野など、脳内の特定部位の障害や、前頭葉-皮質下回路の障害、セロトニンやドーパミンを神経伝達物質とする神経系の機能亢進が推定されています。 大脳基底核(淡蒼球・両側尾状核)の体積減少など脳の形態学的変化も認められます。
遺伝に関しては第一度親族に強迫性障害が見られる場合、障害発生率は10-20%となり、また一卵性双生児による一致率が60-90%と高いため、軽度の遺伝性を認めます。
パニック障害、強迫性障害の治療
①治療薬は、過剰な神経の暴走と対抗してその働きを弱める、Gaba(ギャバ)作動薬がしばしば使われます。
②過剰な神経の暴走と対抗してその働きを弱める、セロトニン神経系を強くする薬(SSRI)もしばしば使われます。
③ドーパミン神経系が不安を介して悪影響を及ぼすケースでは抗ドーパミン薬も選択肢になります。
④お薬は発作時に頓服で使う方法と、事前に内服して頻度を減らす方法があります。
これらの障害には、トラウマのような過去の記憶が引き金になっていることもあります。ですからお薬以外の治療法には、
①過去の記憶を掘り下げて意識化して克服するカウンセリング治療が有効です。
②現在の心の状態を把握して是正する認知行動療法が有効です。
また、セロトニン神経系は、深呼吸・散歩・咀嚼・リズム体操で活性化されるので、症状の起こる不安を感じた時は、
①ゆっくり深呼吸を繰り返す
②少し周囲を散歩してみる
③ガムを噛んでみる
④軽くリズム体操をしてみる
お薬を使う以外に、このような対処で発作的な症状を防ぐことができます。