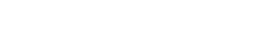子供の不登校と引きこもり
不登校学童は小学校・中学校を合わせると約10万人、ひきこもりは約50万人以上と言われています。
その背景は、統合失調症やうつ病、発達障害、不安障害、パーソナリティ障害と様々です。
こどもの統合失調症
①統合失調症は10歳までの発症は珍しいとされていますが、中学生くらいになるとそれほど珍しくはなくなってきます。
②子どもの場合、発症後の経過はゆっくりで、不登校・不安障害・チック障害などの症状を経てから統合失調症が出てくる場合も多いようです。
③しかし高校生ごろからは症状の進行が速くなり、イライラや強度の不安感、または怒りっぽくなるなど情緒不安定目立ってきます。
④最終的には恐怖や不安、妄想、幻覚、幻聴などが現れて時に暴力的になったり、言葉が支離滅裂になってきたりします。
⑤統合失調症の治療は薬物治療が中心で、初期は薬の効果がいい印象です。
発症の初期に適切に処置をすれば、経過が良好である場合が多く、何か気付いたことがあればためらわずに医師の診察を受けることが望ましいと言えます。
こどもの気分変調症
思春期からの気分変調症は実は大変ありふれた病気です !
◎思春期に気分変調症を発症すると、単に「難しい年ごろ」「思春期の悩み」程度ですまされてしまう場合が多く、このようなケースでは、自分自身では『気分変調症』という病気にかかっているなどとは自覚していませんし、周囲にもこの病気への理解が欠如して、回復を遅らせる要因となっています。また気分変調症の方には、物心がついてからずっと暗い気持ちに苦しみ続け、極端な場合「自分は生まれながらにして不幸な運命だった」と思い込み、実は相当深く悩んでいる場合も多いのです。
◎統計的に、一生涯で気分変調症を患ってしまう方の割合は、人口の約6%といわれ、女性には男性の2〜3倍多いとされていますが、小児では性差がないといわれています。計算上は男性では20~30人に一人が、女性では10人に1人がこの病気に『気分変調症』かかっていることになります。
◎気分変調症が悪化して『うつ病』のレベルになると、「気分が暗くなった」「以前と人柄が変わった」と自覚的にも他覚的にも分かりますので、精神科等での治療開始につながることが有るのですが、気分変調症の初期段階は、多くのケースが思春期にひっそりと始まり、成人してからもずっと持続していて、うつ病という病気の前兆ではなく「性格の問題」として見過ごされている場合が多いのです。この点がこの病気の治療を遅らせる問題点と指摘されています。
◎一般に『気分変調症』という病気の治療を希望して医療機関を受診する方はほとんどいません。気分変調症の方が成人して、ストレスの多い環境下でさらに急性のうつ病を患って、「二重うつ病」という重篤な状態になってから初めて精神科を受診するに至ることが多いのです。
◎報告では精神科の初診時に、すでに59%が「二重うつ病」に罹っていたとされています。さらに慢性化すると、治療経過中に全体の97%もの患者さんが大うつ病性障害を発症してしまうようです。思春期には見逃されていた『気分変調症』の患者さんのほとんどが、大うつ病性障害を合併して、より重篤で自殺の危険もある「二重うつ病」を合併してしまう事は看過できない事態です。
◎思春期以降の早期に気分変調症を発見するには、繰り返して頭痛や腹痛を訴えたり、不登校の傾向が有る場合に、安易に考えずに『気分変調症』という病気の有ることを念頭に慎重な対処をする事が重要と思われます。特に、下記のような心の傾向があるときには注意が必要です。
・自分は何をやってもうまくいかない。
・自分は人間としてどこか欠けている部分があると思う。
・自分以外の人は苦しいことにもよく耐えているのに、自分には耐えられない。
・自分は自分自身を不幸で弱い人間だと思っている。
・自分は何か、自分がやるべき努力を怠ってきているように感じる。
・他人が「本当の自分」を知ってしまったら、きっと私を嫌いになるだろうと思う。
・私が「○○をしたい」というのは、大抵がずいぶんわがままなことだと思う。
・自分が何かを言って波風を立てるくらいなら、言わずに我慢した方がずっとましだと思う。
・自分の人生がうまくいかないのは、自分が今までちゃんと生きてこなかったからだと思う。
・人生は苦しい試練の連続であり、それを楽しめるとはとても思えない。
・これから先の人生に希望があるとは思えない。
思春期に限らず、上記のような悩みのある方は、ぜひお早めにご相談下さい。
当院では薬物療法と【認知行動療法】を併用して、短期間で症状が改善するように早期の治療を呼びかけています。当院では思春期の心の問題を診療する専門外来を完全予約制で行っています。思春期外来は原則として親と子どもの両方に心の治療を行いますので、親子でのご来院をお願いします。
一般的な不登校の経過は、以下のような経過をたどることが多いと言われています。
①まず不登校や引きこもりの火種がくすぶっている状態(学校や会社など社会でなんらかの葛藤を抱えている状態)では、葛藤がまだ表面化しておらず、 言い換えると葛藤を抱えながらも登校できている段階ですので、周りはほとんど認識することはできません。もちろんこの時期にうまく葛藤が処理される場合も 多く不登校や引きこもりにならず経過されている場合も多いと思います。
②しかし、葛藤がうまく処理されず、不登校や引きこもりが表面化した場合は、激しい葛藤が表面化し、家庭内においても不安定さが際立ちひどい場合は 家庭内暴力などの問題が噴出します。この時期はできるだけうまく親子関係などを維持することが大切となってきます。もちろんこの時期においても次の段階に 進まずに短期間で不登校や引きこもりを脱する場合もあります。
③その後、不登校やひきこもりが持続する時期が訪れます。この時期は家庭内暴力などの激しい症状は後退し、ひきこもりがより顕著となる時期でもあり ます。徐々に余裕を取り戻し、大半の場合は最後の段階に入っていきますが、できるだけ早くこの時期を脱することが予後に関わってきます。
④最後に、学校や会社などの社会に再度関心が芽生え、不登校やひきこもりを脱することとなります。この最後に時期において周りの最後の一押しが必要となってくる場合があります。
不登校・ひきこもりの対応ですが、
①顕在化した症状のケアなどを通じて子どもの心の訴えに耳を傾け対処することが大切です。
②当事者には休養が、家族やその他の関係者には余裕が必要な時期であり、支援者が過度に指示しすぎないことが肝要です。
③焦らずに見守る、性急な社会復帰の要求は避ける、家族の不安を支える、適切な治療・支援との出会いに配慮が必要です。
④お子さんの変化に一喜一憂せずに安定した関わりを心がけます。
などがあげられます。
◎しかし、不登校・ひきこもりは、1つの観点からではとらえがたい現象ですので、1つの側面への支援だけでは支えきれません。
◎1つの機関だけで支援を最初から最後まで全てを担当することは難しいのが現状ですので、機能の異なる他機関との連携を常に意識しておくことが大切です。
◎不登校・ひきこもりの支援には地域が持つ使用できる方法はなんでも使用するという柔軟な対応と同時に粘り強い対応が必要となります。
こどもの生育歴とストレス耐性
◎生育歴で虐待等のストレスに曝された子供では、扁桃体と海馬の発育が阻害されていることが示唆されています。デューク大学とダーハムVA医療センターの研究発表によると、戦地から戻った兵士でPTSD(心的外傷後ストレス障害)と診断された人たちの脳は、恐怖や不安をコントロールする扁桃体の大きさが有意に小さいことが判明しました。
2012年の”Archives of General Psychiatry”誌第5版に発表された報告によると、心的外傷の激しさの如何に関わらず、扁桃体が小さい人がPTSDに罹患しているのが分かりました。しかし、果たして扁桃体が小さいためにPTSDが起きているのか、あるいは小さな扁桃体は心的外傷の結果として後天的に生じたのかはまだ解明されていません。
私たちは愛情に満ちた生育歴を持たない子供では、扁桃体と海馬の発育が不十分で、そのために心的な外傷に対するストレス耐性が弱くなっていると考えて研究を進めています。
◎私が2010年に示した、側坐核と扁桃体による行動選択のシェーマに従うと、
http://www.blog.crn.or.jp/report/04/65.html
『外部からの刺激信号は、大脳皮質感覚野で連合された情報として扁桃体に提示され、そこで生物学的な良い・悪いの評価を受けます。また個体内部での環境変化情報も同じくこの経路で生物学的な良い・悪いの評価を受けます。これらの情報は海馬に記憶データとして蓄積され、常に照合と書き換えが行われています。これらの情動的な(本能的で無意識の)判断による行動が、例えば美味しい餌を獲得したとか、良き生殖相手と関係を結べたなど、動物の生存・繁殖にとって有利な結果に導かれた場合には、腹側被蓋野からのドーパミン神経系が側坐核に対して報酬信号を送り、その行為を記憶して反復するように学習・記憶の設定が起こります。このようにして学習・記憶された行動は、次に示す大脳皮質-視床-基底核ループ内に行動パターンとして記憶・蓄積され、同じ状況では同じ行動が自動的に発現するようになります。大切なことは、これらの情動的な行動選択はほとんどの動物種では本能的で無意識な自動的選択として実行されているということです。』
◎簡単にまとめると、愛情に満ちた生育歴を持たない子供では、扁桃体の発育が不十分で、そのために生物的(あるいは本能的)に自分に良いものと自分に悪いものとの判断が出来ず、自分自身の行動を制御する能力が欠けていたり、人格面での発達が不十分で社会性の発達が未熟であったり、ストレス耐性が弱いまま成長したりの総合的な発達障害を起こす原因となっている可能性が高い、といえます。